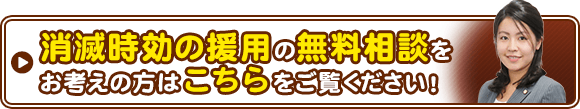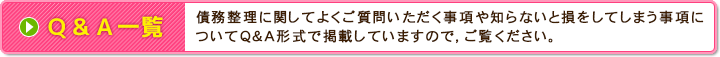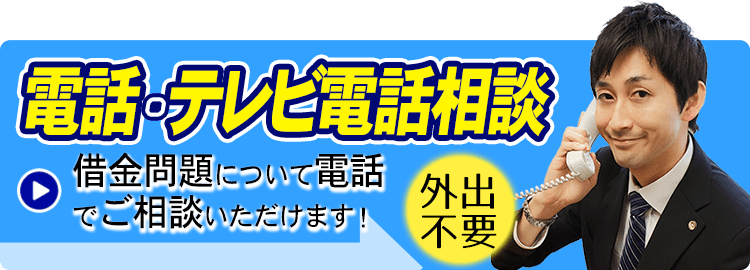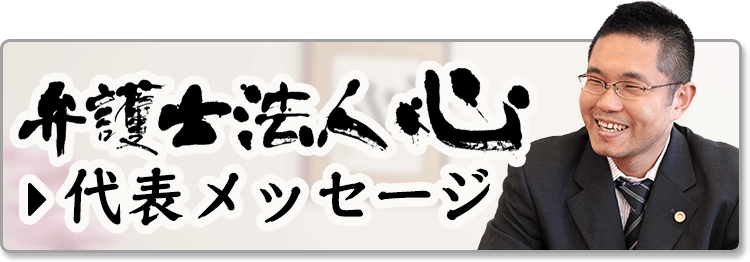「時効の援用」に関するお役立ち情報
裁判になった場合の時効の援用
1 消滅時効は自動的に成立するわけではない
銀行やカード会社からの借入れについては、最後の借入れあるいは返済から一定期間経過すると債務が消滅する制度があります。
これを消滅時効と言います。
通常ですと、銀行やカード会社からの借入れの場合消滅時効が成立する期間は5年間となります。
但し、気を付けなければならないのは、最終取引から5年間経過すれば、自動的に債務が消滅するというわけではなく、債務を消滅させるためには「時効の援用」(=時効が成立し債務は消滅したとの意思表示)を行う必要があります。
2 訴訟対応を誤ると債務は消滅しない
消滅時効成立に必要な期間が経過していても、時効の援用をしなければ債務は存続し続けることになります。
そして、時効の援用をする前に債権者が訴訟を提起し、裁判所が「支払い義務がある」という判決を出してしまうと、せっかく消滅時効成立に必要な期間が経過していても、時効の援用ができなくなってしまいます(判決が確定すると、今度は判決確定から10年経過しないと消滅時効を主張できなくなります。)。
そのため、消滅時効成立に必要な期間が経過していたとしても、債権者が訴訟提起をしてきた場合には、適切な対応をしなければなりません。
3 訴訟提起された場合の対応方法
重要なことは、消滅時効成立に必要な期間が経過している場合、訴訟を提起されただけであれば、時効の援用をすることはまだ可能であるという点です。
訴訟を提起されたことで慌ててしまい、債権者に「支払いはしますので時間をください」等と支払い意思を示してしまうと、それが理由で時効の援用ができなくなることがあるので注意が必要です。
訴訟は、原告・被告双方がそれぞれの主張を出し合うことができます。そのため、債務の支払いを求める原告(債権者)側の主張に対して、被告(債務者)側は「時効の援用をするので支払い義務は消滅した」という反論を行うことができます。
時効の援用の場合、債権者への通知方法に関して特段決まりがあるわけではありませんので、訴訟手続きの中で自らの主張書面の中に記載する形でも構いませんし、訴訟手続きの外で債権者へ内容証明等の郵便によって時効を援用する方法でも構いません。
通常ですと、消滅時効の成立に必要な期間が経過していることに争いがない場合には、債権者は時効の援用を受けると訴えを取下げ、以降は督促も来なくなることが多い印象です。